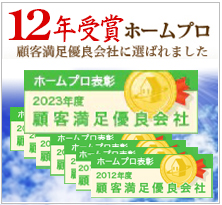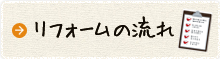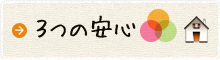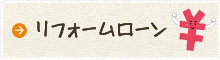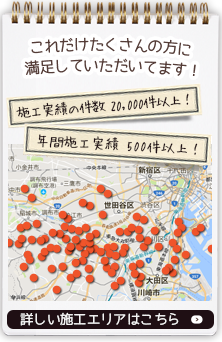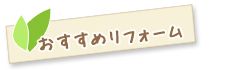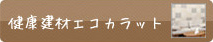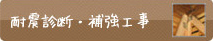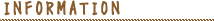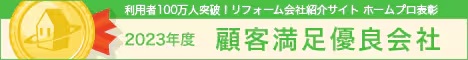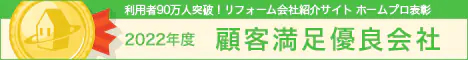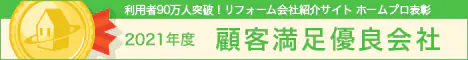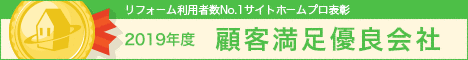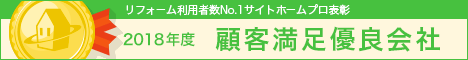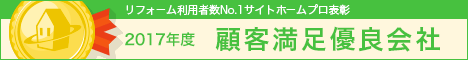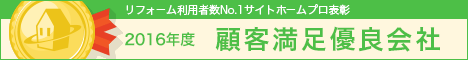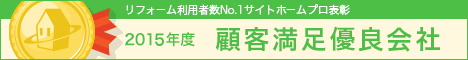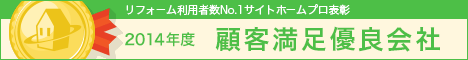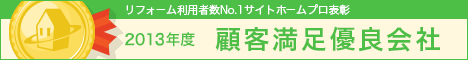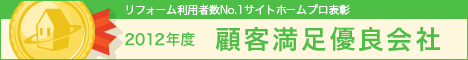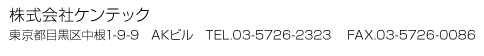スタッフ日記
バリアフリー住宅です
営業の小川です 。
。
先日工事が終わったお宅をご紹介します。
このマンションは高齢者用の分譲マンションで、
一定年齢以上の方でないと入居できません。
もともと和室とカーペットでバリアフリーになっていたのですが、
ご入居にあたり2LDKから1LDKにし、防音フローリングで工事をしました。
畳を撤去したところは、他の床のレベルにあわせて、床下地を作り、
床に段差ができないようにしました。
工事中は、安全に他の居住者の方々の安全に気をつけたり
皆さんがお食事をされにダイニングヘ行かれるので、
その時間はエレベーターを使用しないようにしたりと
注意する点が多かったのですが、居住者の方々も気持ちの良い方が
多く、騒音等かなりご迷惑をお掛けしたにもかかわらず
皆さんが気持ちよく挨拶をしてくれて、とても嬉しかったです。
今日そのお宅に伺ったのですが、新しい生活を楽しんでいらっしゃるようで
とてもよかったです。
施工前です!


施工後です!
エアコンクリーニング
こんにちは。
寒い日が続いております。少しずつ春に近づいているはずですが、なかなか暖かくなりません。
さて、そんな中使用頻度が増えてくるのがエアコンです。確かに冷房運転の方が、水(ドレン水)もでて汚れ易いように感じますが、冬も意外と汚れます。特に乾きが悪いからと部屋干しして暖房等を作動させてると、通常の運転に比べて汚れやすくなるそうですのでお気をつけ下さい。
湿気を含んだ汚れはモーターの周りで乾燥して固まり、どんどん汚れが吸着していきます。長年使用した換気扇がカラカラ音がしてくるのも、原因の多くがこの汚れがファン部分に接触しているからだそうです。
そこで、汚れがこびりつく前にエアコンのクリーニングがお勧めです。
お掃除前

お掃除後
今年の夏は暑くなるのでしょうか。
お掃除はゴミも出ない一番クリーンなエコ対策です。
花粉症対策!!
そろそろ花粉症がひどくなるシーズンですね~
最近は、くしゃみが連続でではじめました。。
毎年、鼻詰まりに悩まされているのですが、そんな悩みに効く?ツボがあると
きいて実践しております。
効き目は・・・。
まだわかりませんが、なんかいい感じです
何事もチャレンジ。
今年はこれで乗り切ろう!!
はーるよこい
2月中旬も過ぎましたがまだまだ寒い日が続きますね。
去年の今頃は 熱海・小田原の梅園は観光客でにぎわっていたように思いますが・・・・・・記憶が定かでない
ニュースで見る限り 人もまばら 梅の花もちらほら さみしい光景ですがこんな調子でいけば 桜の開花も遅く 春は程遠いのでしょうか
今年青森弘前城の桜を見に行く予定をしているのですが 時期的に何時ごろ見ごろになるか気になります。
地球はミニ氷河期という説もあり 世界中で異変があるのも心配です。
はーるよこい はーやくこい 
まさかの珍事件
こんにちは、アドバイザーの板倉です。
まだまだ寒い日が続いていますね、陽が射すとポカポカなのですが
日陰で風が強い日はもう手がかじかんでたまりません。
先日、横浜の現場で浴室の工事を行わせていただきました。
タイル張りの在来浴室で2階に設置されており、今回ユニットバス
に変更ということで浴槽の搬入が大丈夫かな?と当日までハラハラ
していたのですが、無事部屋内で搬入も出来、まずはひと安心。
…のハズだったのですが、ユニットバス組立の2日目に思わぬ出来事が。
なんと飼っている猫ちゃんが浴槽のエプロン点検口から床下にもぐって
しまったのです。
作業期間中は危険ですので洗面室・浴室の入口を閉めておいたり、
バリケードのようなものを設置したりと注意していたのですが、
何らかの拍子で明け方早くに好奇心に駆られて潜っていってしまった
ようです。
結局その日は猫ちゃんが出てくるのを祈りつつ作業を中止して日程を
ずらしたのですが、まさかの予期せぬハプニング。
でも猫ちゃんも当日中に無事姿を現してくれましたので良かったです。
工事も無事完了し、スッキリしたさわやかな浴室に生まれ変わりました。
ペットを飼っているお客様のお家の工事はより慎重に養生と配慮が必要
だと改めて痛感した現場でした。ありがとうございます。
それでは。